○短編パノラマ


A Family Portrait、Tussilago
A Family Portrait (Joseph Pierce)はシュトゥットガルトでグランプリを取るなど、今年の話題作の一つだったが、ここではパノラマの上映。スタンダップ・コメディアンを取り上げた卒業制作Stand Up同様に、実写をベースとして、人々の顔をグロテスクにひん曲げていく手法を用いている。今回取り上げるのはうさんくさい写真家に家族写真を撮ってもらう家族の話。写真用の取り澄ました表情が、芸術家ぶった写真家のあほらしい要求によって次第に壊され、家族間の互いの真なる表情がむき出しになっていく。聞くところによれば大山慶の作品や春画を愛しているらしく、確かにそれは頷ける話である。
Tussilago (ジョナス・オデルJonas Odell)は、若気の至りからドイツ赤軍のテロリストと交際し行動を共にし、結果として生涯のほとんどを獄中で過ごすこととなってしまったAという女性の回想をアニメーション化したもの。アニメーションとドキュメンタリーは2000年に『ウェイキング・ライフ』で哲学的ダイアローグがアニメーション化されたあたりから少しずつ世界各国で見られるようになり、オデルの作品でいえば4つの「初体験」物語を当人のナレーションを用いてアニメーション化したNever Like the First Time!やLiesがまさにその流れの「流行り」の時期にあたるものだった。(ジョン・レノンのインタビューをアニメーションにしたI Met the Walrusや日本だと『おはなしの花』などといった傍流の作品もあった。)去年のアヌシーでグランプリを受賞したSlavarや『戦場でワルツ』あたりがその最大の盛り上がりだったといえるだろうか。アニメーション・ドキュメンタリーは今ではひとつのジャンルとして定着した感もあるが、オデルはTussilagoでもう一度正面からこの手法に取り組んでいる。しかし気になってしまうのは、語られる物語と映像のスタイルとの乖離である。端的に言ってしまえば、Liesの最後のエピソードからそうだったのだけれども、語られる物語があまりにも重すぎて、それだけで充分に完結してしまっているように思えるのである。映像はどんどんと達者になっていくけれども、単なるファッションに堕してしまっているような……語りに負けているのである。
○学生コンペから
今年の学生コンペはバラエティに富んでおり、魅力的な作品が並んだ。
・プログラム1


『わからないブタ』、『ミラマーレ』
Look Up (Svetlana Podyacheva)はこの二作と比べると現代的ではまったくないが、いかにもロシアらしい良作。みなが下を向く街のなかで、上を向く少女が巻き起こすちょっとした騒動を描く。ロシアらしさとは何か? ソユズムリトフィルムの伝統を意識的にか無意識的にか内容的にも手法的にも引き継ぎ(この切り絵作品は手法的にはノルシュテインを、少女の内的リアリティが街の人々に共有されていくという点では内容的に『ミトン』を思わせる)、根本のベースに内向性と調和性がある世界を描くことだ。
プログラム一番の衝撃は『ホーンテッド・ハート』Haunter Heart(ウィノナ・リーガン Winona Regan)。男と女のあまり幸せそうではない情事を歌を歌いながら窓から覗き込む双子(?)の少女二人。この作家はパルンやコヴァリョフから影響を受けているようにも思える。しかし、自らのスタイルに意識的な彼らとは異なり、この作品についてはどこまでが「天然」の産物なのか見分けがつかない。ただ見終わった後には、少女たちが歌うあの不思議な歌がこびりついて離れなくなるのである。
プログラムもうひとつの「天然」系、『生命線』Lebensader(アンジェラ・シュテッフェンAngela Steffen、特別優秀賞受賞)はもはやお馴染みのクラシックな風格漂うノンナラティブ作品。生と死が絡まりあった獣として世界と捉える試み。『愛と剽窃』で中割りを担当した彼女は、今年のアヌシーの裏MVPであるともいえるかもしれない。
・プログラム2


『悩ましい愛撫』、Jeu En Jeu
A Moving Business (Falk Schuster) は良い感じで力の抜けた人形アニメーション。広告で宣伝されたものをなんでも欲しくなってしまうおじさんと、それによって被害を被る隣人のおばさんの物語。どうしようもない人間の愛らしさをそのまま受け止める作品で、もしかするとこういった世界観も近年のひとつの傾向かもしれない。(たとえば、アダム・エリオットも和田淳も、自分で自分を律することができない存在として人間を描き、でもそれでいいのだと言っている。)
続くJe En Jeu (Guillaume Bourrachot) は、二人の俳優と演出家のあいだの、外から見るとバカらしいが本人たちは至極まじめなリハーサル光景と本番の出来事を描くアニメーション。暴走する演出家とそれに戸惑う俳優二人のあいだの空気感や距離感が笑いを誘うが、最後の本番での予期せぬダンスは美しくて息を呑む。
・プログラム3

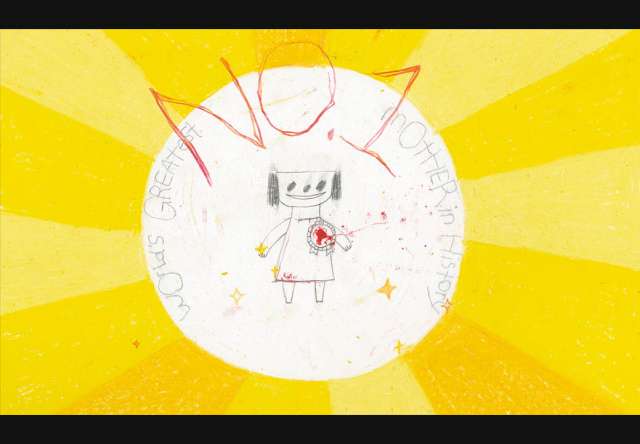
Viliam、『view』
The Lighthouse Keeper (David Francois, David François, Rony Hotin, Jérémie Moreau, Baptiste Rogron, Gaëlle Thierry, Maïlys Vallade、最優秀賞受賞)は「The ゴブラン」という感じのハイクオリティ・ファンタジー。灯台の光に誘われて巨大な虫がやってくる、という言葉にしてしまうとどうでもいい物語が、映像の質の高さによって観客を強く引き込む。
Viliam (Veronila Obertova)は切り絵立体の良作。絵を描くことが大好きで、自分の空想を絵にすることによってその世界に暮らしつづける少年ヴィリアムの世界は、彼を守りつづけてきた両親の死とともに崩壊する。強烈な空想力を一挙に潰しにかかる現実の容赦ない力。絵は水を垂らされれば消えてしまう。こんな当たり前の事実がこれほど残酷さを体験させるものとなるなんて。
『ベニーニ』Benigni (Elli Vuorinen, Jasmini Ottelin, Pinya Partanen)は心温まる人形アニメーション。巨大化する人面疽を切り取ろうとするとそこに顔が浮かび上がってきて……ダメ人間とピュアな人面疽の交流は、あたかも最愛のペットと親密な時間を過ごしているような感覚を観客にも抱かせる。
Parade (Pierre-Emmanuel Lyet)は去年でいえばChickの枠にあてはまるような作品か。スチル写真はまるでマクラレンの切り絵作品のようにデザイン性が迷いなく高く、作品自体もセンスよくまとめているのだけれども、何度観ても物語が入ってこない。
Fly on the Window (Nikita Diakur)は近年のRCAには珍しい3DCG作品。最近のRCA作品ってなぜか「白い」ものが多いのだけれども、これも白い。この作品はアプローチが面白い。同じ世界を共有するハエ、人間、犬、魚の目から眺められた世界が何の説明もなく入れ替わっていく。舞台は二棟のマンションとその周辺ということで決して広い場所ではないのに、世界を俯瞰する気などまったくない主観的なカメラワークが、世界の広がりを無限に感じさせる。心地よい突き放され感があるのだ。複眼のハエ目線で歪む世界が愛おしいほどに美しい。アニメーションだからそんなわけはもちろんないのだけれども、機械の目が捉えた、意味付けされない平等な世界を眺めているような感じになる。作品自体としては少し失敗しているのだが、持っているポテンシャルは非常に高い作品。
『View』 (ナユン・リーNayoon Rhee)は衝撃のビジュアルで迫ってくる作品。母親から捨てられる子供の内的世界が、子供の落書き調のぶっきらぼうな描画で描かれる。作家本人によればこの作品は別に自分の実体験から着想されたものであるというわけではなく、ただ単にエンタテインメントとして作ったもののようだ。アニメーションのこともそれほど詳しくないらしく、だからこそ可能になる突き抜け方をしているということか。
・プログラム4


Prayers for Peace、『オルソリャ』
Un Tour de Manege (Nicolas Athane, Brice Chevillard, Alexis Liddell, Francoise Loisto, Mai (Phuong) Nguyen)もまさにゴブランという作品。商売としても充分に通用するクオリティの高い描画を用いた、手描き感あるCG映像。メリーゴーラウンドが人生の輪廻を象徴し、『岸辺のふたり』を彷彿とさせないこともない。
『指を盗んだ女』(銀木沙織)は多彩な作品が並ぶ今回の学生コンペにおいてもやはり異色。たとえば『Maggot』がそうであったように、静止画であっても充分に音楽的で画面が活きているというレベルには到達していないなど、どうしても「粗さ」が残っているのが気になってしまうが、人間に潜むマイナスの、しかしとても強烈な感情(この作品でいえば母から子への支配欲・所有欲)を触感的な展開によって情動的に描くという点で、あまり類する作品を観たことがない。
Yellow Belly End (Philip Bacon)は色々な場所で受賞している話題作。ジブリのロゴのパロディで始まり、全体的にポップでオシャレなビジュアルが広がる。何をしているのかよくわからないけれどもなんとなくは理解できるという、説明しすぎない良さというものが光る。ある意味和田淳の『鼻の日』的ではあるが、こちらはかなり軽やかだ。
『オルソリャ』Orsolya(ヴェッラ・ゼデルケニイBella Szederkenyi)は作品の世界観としては、トーリル・コーヴェ直系に思えるけれども(主人公たちの人生を俯瞰する感じが特に)、しかし登場するキャラクターたちはおそらくアダム・エリオットと近い。エリオットが奇妙で醜い人形の造形によって人間の本質的な不完全さを表現するとすれば、『オルソリャ』は、逆立ちしないと歩けなくなってしまった女性という設定でそれを補う。あるとき原因も分からず世間とズレてしまうという設定自体は『スキゼン』とも共通するが、救いがなかったあの作品よりかは、クラパンでいえば『バックボーン・テール』に雰囲気は近いといえば分かっていただけるだろうか。不完全なものが自分たちの不完全を認識したうえで、他者と寄り添いあうラストは非常に納得のいく希望を感じさせてくれる。
○長編コンペから

『ファンタスティックMr.Fox』
実写映画界ではすでに充分なキャリアを重ねているウェス・アンダーソンの初めてのアニメーション作品。『ライフ・アクアティック』ではヘンリー・セリックを起用してクレイ・アニメーションを用いたり、作品自体も絵作りのしっかりとした監督であったので、アニメーション制作に携わることはそれほど意外なことでもないと言えるだろう。従来のアニメーションの文脈とは違うところに属する人が、アニメーションの未知なる可能性を発見することは近年よく見られるが、この長編もそんな例に数えられるのではないか。ロアルド・ダール『父さんギツネバンザイ』を原作とするこの作品は、アンダーソンの他の映画と同じくやはり父と子の関係を描いているけれども、ビル・マーレイが大写しになるのと同じような感覚でキツネたちもクロースアップになり、リアリスティックに感情の機微を描いたかと思えば、「パニック・イン・ザ・ヴィレッジ」並に適当にもなる。このコロコロとリアリティが変わる感じもやはり実写と変わらない。アニメーションで何がやりたいのかが明確に見えているというか、実写でもアニメーションでもやっていることは同じと言うか。
ただ、アニメーション側の観点から見てみると、人形に対してこれほどカラッとした距離感を保っている立体アニメーションも珍しい。もちろん愛がないというわけではなくて、この距離感こそが、アンダーソンにとっての愛なのだろう。個人的には完全なる箱庭感が息苦しい『ダージリン特急』よりは箱庭の外側の世界に降り注いできて呆然とさせられる(それにはセリックのアニメーションも一役買っていた)『ライフ・アクアティック』の方を断然支持する人間としては、『ファンタスティック・Mr. Fox』は前者の方向性なのが少し残念だ。そっちの方向性なのはアニメーションなんだから当然だろうと思うかもしれないけれども、だが個人的には現代のアニメーションの強みとは『ライフ・アクアティック』が示すようなビジョンなのである。とはいえ非常にユニークな人形アニメーション作品となっていることは変わりないので必見だ。
・Piercing I (Liu Juan)

Piercing 1 ![]()